巻17第10話 僧仁康祈念地蔵遁疫癘難語 第十
今は昔、京に祇陀林寺という寺がありました。その寺に仁康という僧が住んでいました。横川の慈恵大僧正(良源)の弟子です。因果を信じて、三宝を敬い、戒行をたもち、仏のように人々をあわれみました。
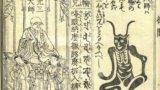
治安三年(1023年)四月、京に伝染病が流行りました。命を落とす者も多くありました。道に死体が隙間なく横たわっていました。身分の別なく、あらゆる階層の人が空を仰ぎ歎きました。
そのとき、仁康の夢に一人の小僧があらわれました。端厳な(美しい)小僧でした。僧房に入ってきて、仁康に告げました。
「おまえは世が無常であることを知ったか」
仁康は答えました。
「昨日会った人が今は会えず、朝に会った人が夕に失われることもあります。私の命が失われるのも決して遠いことではないでしょう」
小僧はほほえみ、言いました。
「世が無常であることは、愁うべきことではない。もしおまえがこれを恐れるならば、地蔵菩薩の像を造り、その功徳を讃歎するとよいだろう。そうすれば、五濁に迷う人々を救い、三途に沈む人によりそうだろう」
それを聞くと、目が覚めました。
仁康は道心を発し、すぐに大仏師康成(康尚)の家を訪れ、地蔵の半金色の像を造る相談をして、やがて開眼供養しました。その後、地蔵講(地蔵に関する講話を聞く会)をはじめました。僧も俗も、男女にかかわらず参拝し合掌し、縁を結びました。
その間、寺の内や僧房の内に、疫病の被害はありませんでした。また、仁康に夢のお告げがあったことを聞いて懇意になった人や横川の人々、講に参加して縁を結んだ人には、病にかかる人はありませんでした。「まったく希有なことだ」といわれ、地蔵講はいよいよ繁昌し参加者が増えたといいます。
仁康は八十歳で命終るときも、まっすぐな心を持っていました。西(阿弥陀浄土があると信じられた方向)に向かい、阿弥陀仏、そして地蔵菩薩の名号をとなえ、眠るようにして逝きました。
現世および来世の利益は地蔵菩薩の誓にまさるものはありません。「世の人は信じ奉るべし」と語り伝えられています。
【原文】

【翻訳】
草野真一
【解説】
草野真一
祇陀林寺は現存しないが、地蔵講はとても有名だったそうで、その縁起譚として伝えられている話。
治安三年(1023年)と記されているが、『今昔物語集』に年号表記がある物語が収録されるのはとてもめずらしいという。
記録にはこの年の疫病流行はなく、2年後に赤斑瘡が流行したとある。赤斑瘡は今で言うはしかだが、天然痘よりはるかに死亡率が高く、江戸時代には〈疱瘡(天然痘)は器量定め、麻疹(はしか)は命定め〉といわれ恐れられていた。
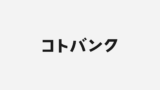
伝染病が流行すれば、この世ならぬものを考える人も増える。宗教が流行るのは道理だ。
ただし、こういうニュースもある。

講は新たな形が求められている。








コメント