巻23第26話 兼時敦行競馬勝負語 第(廿六)
今は昔、右近の馬場において競馬(くらべうま)が行われたとき、その第一番の組に尾張兼時(おわりのかねとき)と下野敦行(しもつけのあつゆき)とが乗りました。
兼時は競馬の騎手として、素晴らしい巧者でした。
昔の名手に少しも恥じないほどの乗り手であります。
ただし、荒馬に乗ることに関しては、いささか苦手でした。
敦行は、荒馬であっても少しも気にかけません。
なかでも、鞭競馬(むちくらべうま・二頭の馬を前後に立たせ、あとの馬に鞭を入れるのを合図に前の馬も出走する競馬。普通の競馬では、一線に位置させ、鼓を打って出走の合図とする)では、素晴らしい名手でありました。
ところで、その日の競馬に、敦行はよく調教されて進退・動作がすぐれた馬に乗っていました。
兼時は、宮城という有名な暴れ馬に乗りました。
この宮城は、素晴らしく足は速いのですが、ひどく暴れるので、兼時の乗る馬としては、まったくふさわしくないのに、兼時はどう思ったのでありましょうか、その日の左方の一番にこの宮城を選んで乗りました。
さて、三度の足ならしが終わり、両馬、触れあうように一組になって乗り、走らせました。
この宮城はいつものこととて、まるで曲芸の玉を取るように跳ね上がるので、兼時は普段の素晴らしい競馬の腕前を発揮できず、ひたすら落馬すまいとするばかりで、どうすることも出来ずに負けてしまいました。
競馬には、二人一組で乗る時から、勝ったあとの乗り方まで多くの作法があります。
けれども、負け馬の退場法にはこれといった先例もなく、その作法を知る人もまったくなかったのですが、その日、兼時が負けたあとの乗り方を見て、すべての人は、「たとえ完敗しても、そのあとはこのように乗らねばならぬものだ」と思いました。
どういう作法なのでありましょうか、すべての人に、「まことに気の毒だ」と思わせるような姿をして乗っていきました。
ということは、「兼時は『負け馬に乗る作法をすべての人に見せてやろう』と思い、わざとこのように宮城に乗り、ことさらに負けたのではなかろうか」と、人びとは疑いました。
これ以後、身分ある者も近衛舎人も、負け馬に乗る作法は、こうするものだと知るようになりました。
実際、このように疑われたのは当然であります。
兼時は、悪馬である暴れ馬に乗ることには心もとないのに、わざと宮城を選んで乗ったというのが不可解であります。
だから、その日、兼時は自らすすんで負けたのだと、世間の人は皆、ほめたたえた、とこう語り伝えているということです。
【原文】

【翻訳】 柳瀬照美
【校正】 柳瀬照美・草野真一
【解説】 柳瀬照美
本話は、事実譚らしい。
負けても素晴らしいと褒め称えられた、競馬に熟達した常勝騎手・尾張兼時の逸話。
近衛府は、六衛府の一つで、内裏の正殿・紫宸殿や天皇の日常の場の清涼殿など、皇居中枢部の警備・儀仗・祭事・供奉などの任にあたった。
長官を大将といい、中将・少将・将監・将曹の四等官の下に、府生・庁頭・庁沙汰人・番長などが置かれた。
舎人には、楽人・舞人のほか、騎射・相撲などをよくする者もいて、近衛府の中で最も目立つ存在で、定員は左右各300人だった。
競馬(くらべうま)は、左右近衛府の対抗で、左方には左近衛、右方には右近衛の官人が騎乗して試合する。現在の競馬と異なり、左右一人あて、二人が一組となる。
尾張兼時は、村上・円融朝より一条朝にかけての高名な近衛舎人。
左近衛将曹を経て、長徳4年(998)左近衛将監に任じられ、競馬・楽舞に長じた。道長の子、教通・能信の舞の師ともなった。
下野(下毛野)敦行は、右近衛将監で、馬術に長じ、朱雀・村上朝に最も活躍した近衛舎人。子・孫に高名な近衛舎人を輩出し、彼らは藤原道長・頼通に仕えた。

【参考文献】
小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』
(巻二十三 了)
【協力】ゆかり・草野真一
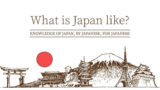









コメント