巻5第8話 大光明王為婆羅門与頭語 第八
今は昔、天竺に大光明王という王がいました。思いやりに深く人に物を与え、五百頭の大きな象にいろいろな宝を乗せ、多くの人を集めてその宝を与えることに対して全く惜しむことをしませんでした。いうまでもなく、宝をせがみにやってくる人達にそれを与えないという事はありませんでした。
隣の国の王がこの大光明王の志を耳にし、王を殺そうとある婆羅門(バラモン)を雇ってその意図を打ち明け、その婆羅門を大光明王のもとへ遣わして王の首を願うよう命じました。婆羅門は大光明王のもとへ行き王の首を願おうとすると、王宮を護る神がこれを知り門番にこれを告げて、婆羅門が宮中へ入らないようにさせました。
しばらくした後、門番は大王にこれを話しました。大王は自ら婆羅門に会いに出向きましたが、まるで幼い子供がその母に会うような様子でした。喜ばしく、なぜ会いに来たのかを婆羅門に尋ねました。「大王の首を与えて下さい」と婆羅門は言います。王は「願いであるので、この首を与えましょう」と応えました。
そして宮中へ戻り、后たちと五百人の太子たちに向けて、婆羅門に首を与えると述べました。后や太子たちは皆これを聞いて悶え苦しんでは気を失い、それが起こらないようにと強くせがみました。しかし大王の気持ちはまったく変わりません。
大王は掌を合わせて十方に向けて礼拝し、「十方の仏菩薩よ、わたしを哀れみ、今日のわたしの願いを叶えて下さい」と自身を木に縛りつけ、「わたしの首を取って与えて下さい」と言ったので、婆羅門は剣を抜いてその木へ向かいました。
その時に樹神が手を上げて婆羅門の頭を打ち、婆羅門は倒れて地面に伏せてしまいました。すると大王は樹神に「あなたはわたしの願いを叶える助けをせず、わたしが善法を行おうとすることの妨げとなってしまっています」と言いました。そのために、樹神は妨げとなることを止めました。
そして婆羅門が大王の首を切り取る間、宮中の后・太子をはじめ大臣、百官、多くの人々がこの上なく嘆き悲しみました。婆羅門は切り取られた大王の首を本国へと持ち帰りました。
大光明王というのは今の釈迦仏であるとされます。婆羅門を雇って命じた隣国の王は今の提婆達多である、そう語り伝えられています。
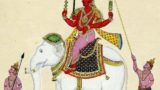

【原文】

【翻訳】 濱中尚美
【校正】 濱中尚美・草野真一
【協力】 草野真一
【解説】 濱中尚美
大光明王について
大光明王はどのように描かれているのでしょうか?
釈迦仏の前世とされる人物なのでどこかにあるんだろうと思ったのですが、グーグル検索する分ではお会いできないようです。
大光明王に近い存在として、ヴェッサンタラ王(シビ王)があげられます。
インド古代史の上で最初の統一国家とされるマウリヤ朝の最盛期を築いたアショーカ王によって紀元前3世紀に建立された釈迦の遺骨を安置する卒塔婆が現在も残されているサーンチー遺跡には、ヴェッサンタラ王とその周りの人々が刻まれています。

大乗仏教と上座部(小乗)仏教
日本での仏教は「布施」を筆頭に「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「智慧」の6つの善を説き、それらは六波羅蜜と呼ばれます。小乗仏教(上座部仏教、タイなどで信仰される)では八正道が強調され、六波羅蜜はあまり説かれず、「布施」をその根幹に含みません。
スリランカ・ミャンマー・タイ・カンボジア・ラオスなど、現在でも仏教を厚く信仰する国では、仏教はどのように扱われたのか。ヒンズー教、イスラム教やキリスト教と交わることで、仏教とは何かという認識が変えられたのかどうか。
布施で知られるヴェッサンタラ王を崇めているということは、じつは大乗仏教もだいぶまざっているのかもしれません。










コメント