巻24第6話 碁擲寛蓮値碁擲女語 第六
今は昔、第六十代醍醐天皇の御代に、碁勢(ごせい)と寛蓮(かんれん)という、碁の名人である二人の僧がいました。
寛蓮は家柄も卑しくなく、宇多院の殿上法師であったので、天皇も常に召して碁のお相手になさりました。
天皇もたいそう上手にお打ちになりましたが、寛蓮には先手を二目お置きになりました。
常々、こうしてお打ちになっておられましたが、ある時、金の御枕を賭けてお打ちになったところ、天皇がお負けなされたので、寛蓮はその御枕をいただいて退出しました。
それを天皇は、若く血気盛んな殿上人に命じて奪い取らせなさいました。
こうして、いただいて退出するのを奪い返させなさることがたびたび重なりました。
その後、またも天皇がお負けになって、寛蓮がその御枕をいただいて退出するのを、いつものように若い殿上人が何人も追いかけてきて奪い取ろうとするとき、寛蓮は懐からその枕を引き出し、后町(きさきまち・後宮の常寧殿のこと)の井戸の中に投げ込んでしまったので、殿上人はみな、去っていきます。
寛蓮は、身を踊らせて退散しました。
その後、井戸の中に人を降ろして枕を引き上げてみると、それは木で枕の形を作り、金箔を押したものでした。
なんと、本物の枕の方は持って退出していたのです。
同じような枕を前もって用意して持っており、それを投げ入れたのでありました。
こうして、その金の枕を少しずつ打ち欠いて、それをもって仁和寺の東のあたりにある弥勒寺(みろくじ)という寺を建立したのです。
天皇も、
「じつに、うまくたくらんだものだ」
と、お笑いになりました。
こうしていつも参内していましたが、ある日、内裏を退出し、一条大路を通って仁和寺へ行こうと、西の大宮大路を牛車で進んでいくと、衵袴(あこめはかま)を身につけたこざっぱりした姿の女童(めわらわ)が、寛蓮の供の童子の一人を呼び止め、何事か話しかけました。
「何を言っているのだろう」と思い、振り返って見ると、その童子が車の後ろに近寄り、
「あれに控えおります女童が、申しましてございます。『この近くの家に、ほんのちょっとお立ち寄りいただきとうございます。申し上げたいことがある、とおっしゃる方がおいでです』と、かように申しております」
と言いました。
寛蓮はこれを聞いて、「誰がそのようなことを言わせたのだろうか」と不審に思いましたが、この女童の言うままに車をやらせました。
土御門大路(つちみかどのおおじ)と道祖大路(さえのおおじ)の交わるあたりに、檜垣(ひがき)を巡らした押立門(おしたてもん・屋根をかけず、左右の門柱に扉をつけただけの門)のある家がありました。
女童が、
「ここでございます」
と言うので、そこで降りて中へ入りました。
見れば、前面に広庇(ひろびさし)のついた板葺で平屋の放出(はなちいで・寝殿造りで母屋から続けて外に建て増しした建物)があり、前庭には籬(まがき)を結い、植込みも趣深く植えられ、砂などがまいてあります。
粗末な小家(こいえ)ではありますが、いかにも風流な住まいであります。
寛蓮が放出に上がると、上等な伊予簾(いよすだれ)が白々と掛けてあります。
秋の頃のことでありますから、夏の几帳がこざっぱりと、簾に重ねて立ててありました。
その簾のそばに、つややかに拭き込んだ碁盤があります。
碁盤の上には、いかにも上等そうな碁笥(ごけ)が置いてあります。
そのわきに、円座が一つ置いてありました。
寛蓮がそこから離れて座っていると、簾の中で奥ゆかしくかわいい女の声がして、
「こちらへお寄りください」
と言うので、碁盤のそばに寄って坐りました。
すると女が、
「あなた様は、当代に並ぶ者のない碁の名手と承っておりますので、それにしてもどれほどお打ちなさるのか、ぜひ拝見したいものと思っておりました。じつはわたくしの父でありました人が、わたくしに少しは素質があると思い、『少し打ってみよ』と言って教えておいて亡くなりましてからは、まったくこういう遊びもあまりいたしませんでしたが、今日ここをお通りになると、なんとなく耳にしましたので、恐縮ですが」
と言います。
寛蓮は微笑み、
「それは、まことに面白いことでございますな。それにしても、どれほどお打ちになりますか。何目ほど、お置きなさいますか」
と言って、碁盤のそばに近寄りました。
この間にも、簾の中から薫物のかおりが香ばしく匂ってきます。
侍女たちは皆、簾越しにさし覗いていました。
そのとき、寛蓮は碁笥の一つを取り、もう一つを簾の中にさし入れると、侍女が、
「□□そのまま、そこにお置きください」
と言うと、女は、
「面と向かっては恥ずかしくて碁なんか打てません」
と言います。
寛蓮は心の中で、「なかなか心にくいことを言うものだ」と思い、碁笥を二つとも自分の前に戻して置き、「女の言い出す言葉を聞こう」と思って、碁笥の蓋を開けて石を鳴らしていました。
この寛蓮は、もともと風流を解し、その方面の心得などもあったので、宇多院も風流のたしなみのある者とお思いになっておられたのでした。
そのため、この女の様子にひどく興味を持ち、おもしろいと思ったのでしょう。
やがて、几帳の隙間から、巻数木(かんじゅぎ・誦経などの際に読んだ経の名や数をしるした紙片を結びつけておく木の棒)のように削った、白くきれいな二尺(約60センチ)ほどの木がすっと出てきて、
「わたくしの石は、まずここに置いてくださいませ」
と言って、中央の聖目(せいもく・天元)を指しました。
「本来なら、何目か置かせていただくはずですけれど、まだお互いの力が分かりませんので、『これも、いたしかたなし』と思い、まずこの一局は、わたくしが先を取りまして、力のほどが分かりましたら、(力の差に応じて)十目でも二十目でも置かしていただきます」
と言うので、寛蓮は女の石を中央の聖目に置きました。
また次に、寛蓮が打ちます。
女の打つ手は木で教えたので、教える通りに打っていくうち、寛蓮の石は皆殺しにされてしまいました。
どうにか生きた石も、駄目を押していくうちに、それほど手厚く打ちもしないのに、おおかた囲まれてしまって、とても手向かいできそうにありません。
そのとき、寛蓮は、「これはなんとも不思議なことだ。この女は人間でなく、妖怪変化の者であろう。わしと対局して、現在どうしてこれほど打てる者があろうか。たとえ、すばらしい名手といっても、こうも皆殺しに打たれるはずがない」と恐怖を覚え、石をくずしてしまいました。
そして、驚きのあまり物も言えずにいると、女はかすかに笑みを含んだ声で、
「もう一局いかがです」
と言いましたが、寛蓮は、「こんな恐ろしい者には二度と物言わぬが良きこと」と思い、草履もはくやはかずに逃げ出して車に乗り、一目散に仁和寺へ帰って院の御前にまいり、
「かくかくかようなことがございました」
と申し上げると、院も、
「いったい誰であろう」
と、いぶかしくお思いになり、翌日その場所に人をやって尋ねられたのですが、その家には誰一人いませんでした。
ただ留守番で、今にも死にそうな様子の女法師が一人いました。
それに、
「昨日、ここにおられた方は」
と訊くと、女法師が言うには、
「この家には左京から方違え(かたたがえ・行くべき方角に悪神がいる方角にあたる場合、前夜に吉方の家に一泊して方角を変えていくこと)のためとかで、五、六日お出でになっておられた方がいましたが、昨夜お帰りになりました」
と答えました。
院の御使いが、言うに、
「そのお出になっておられた方は、何という人か。どこに住んでおられるのか」と。
女法師が答えるには、
「私は、どなたとも存じません。この家の主人は、筑紫(つくし・九州)に下っております。その知り合いの方でもありましょうか。□□存じません」と言いました。
御使いは、其□□なくて終わりました。
天皇(醍醐天皇)も、この話をお聞きになり、ひどく不思議にお思いになりました。
当時の人が言うには、
「人間であったなら、寛蓮と盤を囲んで、どうして皆殺しに打てよう。これは、へんげの者などが現れたのであろう」
と、疑ったのでした。
そのころの世間では、この話で持ち切りだった、とこう語り伝えているということです。
【原文】

【翻訳】 柳瀬照美
【校正】 柳瀬照美・草野真一
【解説】 柳瀬照美
冒頭の一文の『碁勢』は元の資料の『碁聖』、つまり囲碁の達人のことを人名と誤解したもの。
平安時代、碁は双六と並んで人気のある娯楽であった。
当時、碁では並びなき名人と言われた寛蓮にまつわるエピソード二話。
寛蓮は、宇多・醍醐朝の囲碁の名人。
俗名は、橘良利。肥前国藤津郡大村の出身で、越前掾を経て、肥前掾の在任時、宇多天皇の出家に従って自らも出家する。宇多法皇に近侍して寵遇を得た。
延喜十三年(913)、勅によって碁式を作り、献上している。

【参考文献】
小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』
【協力】ゆかり・草野真一


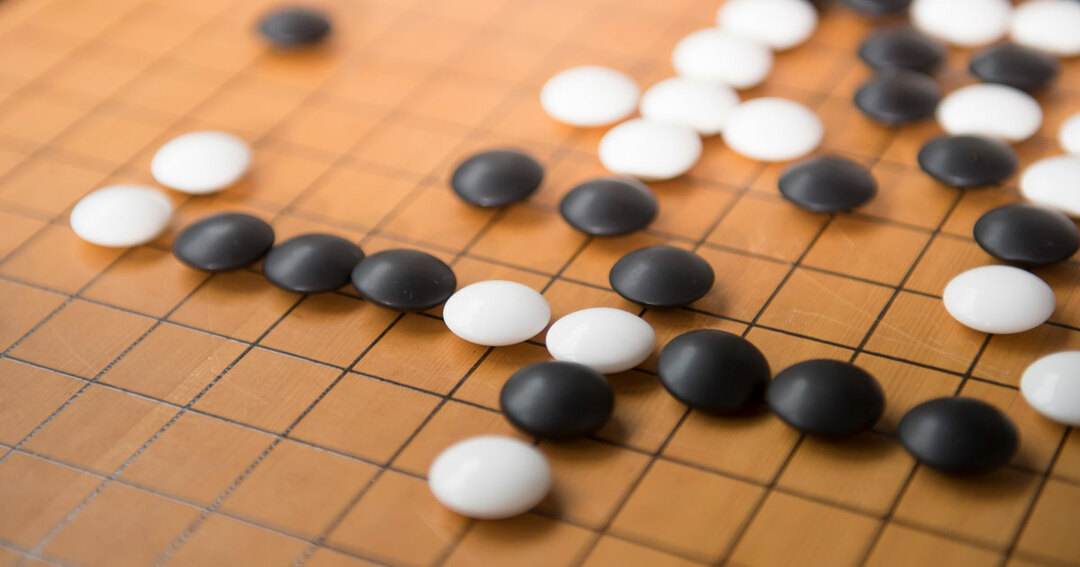









コメント