 English
English20-23 The Holy Man Who Sought Rebirth in Paradise but Became a Small Snake
Once upon a time, in the Yokawa area of Mount Hiei, there was a monk. He had awakened his religious heart and devoted hi...
 English
English 巻十三
巻十三 巻十九
巻十九 巻十三
巻十三 巻三十一
巻三十一 巻十三
巻十三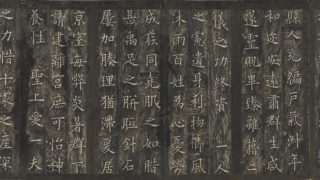 巻九
巻九 第十
第十 第十
第十 English
English 第十
第十 巻十二
巻十二 巻十二
巻十二 巻三十一
巻三十一 第十
第十