巻25第1話 平将門発謀反被誅語
今は昔、朱雀院(すざくいん)の御代のとき、東国に平将門(たいらのまさかど)という武人がいました。
これは桓武天皇の子孫の高望親王(たかもちしんのう)と申す方の子にあたる鎮守府将軍(ちんじゅふしょうぐん)良持(よしもち)という人の子であります。
将門は常陸・下総(ひたち・しもうさ・今の茨城県)の国に住み、弓矢の道をよって立つものとして、多くの勇猛な武士を集め、これを部下として合戦するのを日頃の事としていました。
はじめ、将門の父・良持の弟に下総介(しもうさのすけ)良兼(よしかね)という者がいました。
将門は父の死後、その叔父・良兼とささいなことで行き違いがあり、仲が悪くなりました。
ついで、父の故良持の荘園の所有権争いから、ついに合戦にまで至りましたが、良兼は道心深く、仏法を尊んでいたので、合戦はなんとか避けようとしました。
その後、将門は常に事あるごとに親戚一門とたえず合戦を続けていました。
そのため、あるいは多くの人家を焼き捨て、あるいは多くの人命を奪いました。
このような悪行ばかりをしたので、その近隣の国々の多くの民は農耕もできず、租税労役を勤めるいとまもありません。
そこで、国々の民は嘆き悲しみ、国司の上申書をもってこれを朝廷に報告したところ、天皇は聞いて驚かれ、即座に将門を喚問せよとの宣旨(せんじ・命令書)を下されました。
将門はお召しによって直ちに上京し、自分の無実を申し立てましたが、数度にわたる審議の結果、「将門は無実である」とのご認定があり、数日後、許されて本国に帰ってきました。
その後また、どれほどもたたぬうちに合戦に明け暮れるようになり、叔父・良兼や良正および、源護(みなもとのまもる)、その子・扶(たすく)などと日夜、合戦を行いました。
また、平貞盛(たいらのさだもり・将門の従弟)は、以前、父の国香(くにか)が将門に討たれたので、このおりに家の仇を討とうと思い、当時、貞盛は在京して朝廷に仕え、左馬允(さまのじょう・左馬寮の三等官)でありましたが、その公務を捨てて急きょ帰国したものの、将門の威勢に敵対できそうもないので、本望をとげ得ず、国内に隠れていました。
(その2に続く)
【原文】

【翻訳】
柳瀬照美
【校正】
柳瀬照美・草野真一
【協力】
草野真一
【解説】
柳瀬照美
第二十五巻は、平安武士の棟梁・源氏と平氏を柱とする武者の合戦譚や武勇・功名譚を収録している。天慶承平の乱を冒頭に、平氏・源氏の順で編年的に説話を配置し、前九年・後三年の役によって終わる。
当時の貴族・文人社会では、武者を「『武』という技能に優れた芸能びと」という共通認識を持っていた。よって彼らは兵(つわもの)と呼ばれ、厳密には武士ではない。けれども、後世の私たちから見れば、彼らは立派な「武士」、そのさきがけである。
将門以前
7世紀、大陸では隋が滅び、唐が興った。唐は朝鮮半島の新羅と結び、百済を滅ぼし、その地に軍を駐留させた。危機感を持った中大兄皇子(天智天皇)は唐の脅威に対する防波堤にするため、百済の復興を画策し、救援軍を送るが、天智2年(663)、白村江(はくそんこう・はくすきのえ)の戦いで壊滅的な敗北を喫し、撤退した。
この手痛い経験から、大宰府防衛のために水城(みずき)を築き、地方の首長に命じて軍団兵士制を組織した。それは、律令国家が完成した奈良時代になると、一般農民である公民一戸から一人を徴兵する大規模な軍団となる。
けれども、重い税や労役から農民の逃亡が相次ぎ、大仏の建造、幾度もの遷都、蝦夷討伐などで浪費が続き、国家経済が疲弊。律令制そのものが揺らぐと同時に、大陸からの侵攻の危機が去ったこともあり、この軍制は桓武天皇の延暦11年(792)、廃止され、代わって、郡司の子弟を兵士として選抜、健児(こんでい)として諸国に配置する制度とした。しかしこれも、平安時代半ばまでに自然消滅する。
『DNAで語る日本人起源論』によれば、北海道、対馬、沖縄の3ルートで、この列島へやってきた人びとは、縄文時代には多様なDNAを持つ集団として、各地域で混在していた。また、アイヌ民族と分かるDNAを持つ集団の存在が判明するのは中世、13世紀。現在の日本人と同じDNAが東北から九州まで均一になるのは江戸時代だという。
10世紀の平安時代、将門の生きた坂東(ばんどう)すなわち、関東地方には縄文の頃から住む血族集団、弥生の頃から住む集団、また朝鮮半島からの渡来人で朝廷の政策によって住むこととなった集団、そして一時、強制移住させられ、東北へ帰る許可が出たのちも住み続けている俘囚(ふしゅう)と呼ばれる帰属した蝦夷の集落も在ったと思われる。
『あずま』とは、古くは逢坂の関以東、また伊賀・美濃以東。奈良時代には遠江(とおとうみ・現在の静岡県)・信濃(しなの・現在の長野県)以東。のちには箱根以東のことをさす。
奈良時代でもそうだが、壬申の乱のように中央に刃向う者は東に逃れ、兵を集めて京へ戻るのを常とした。
利根川に育まれた坂東の地は、武蔵・上総・下総・常陸・上野(東京・埼玉・千葉・茨城・群馬)が大国、相模・下野(神奈川・栃木)が上国と位置づけられ、物成りも豊かで、天皇家や藤原氏の牧(牧場)もあった。
班田が行われなくなった延暦年間以降、9世紀中葉には現地に赴任する国司、すなわち受領(ずりょう)が朝廷に貢納物の完納と未進分の補てんの責任を負うようになる。言い換えれば、固定額の貢納物を納めれば、国内で税率を変動させようが、付加税を徴収しようが、受領の取り放題ということになる。
埼玉県行田市にある5世紀末に作られた稲荷山古墳より出土した鉄剣に見られるように、古くから、東の地方豪族は畿内の大王に服属していた。彼らは律令制では郡司となり、中央から派遣された受領は、この郡司富豪層を課税対象とした。そのため、反発した郡司富豪層は、群盗となって蜂起する。
宇多・醍醐天皇の寛平7年から延喜元年に至るまで、東国の群盗蜂起は7年間に及んだ。
また九州北部には新羅海賊が来襲し、畿内、出羽でも群盗が蜂起して、この時期、全国的な騒乱状態となっていた。
これを鎮静化させたのが、群盗追捕指揮官として任命された押領使(おうりょうし)である。押領使は、追捕官符を受けた受領の命に従い、国内の兵を動員して反乱を鎮圧する任務を負う。
寛平・延喜年間に坂東で武名を挙げた人物には、平高望(たいらのたかもち)、「利仁(りじん)将軍」の通称で知られ、芥川龍之介の『芋粥』の登場人物でもある、藤原利仁(ふじわらのとしひと)、後世「俵藤太(たわらとうだ)と呼ばれる藤原秀郷(ふじわらのひでさと)、嵯峨源氏の源仕(みなもとのつかう)、小野氏の高向利春(たかむこのとしはる)がいる。
この『武士の始祖』ともいうべき人びとの中で、平高望は将門の祖父である。
〝力こそ正義〟のこの時代、坂東に土着した平高望の子孫たちは、やがて土地や利権をめぐって私闘を演じるのだった。

[参考文献]
小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』
『DNAで語る日本人起源論』篠田謙一著、岩波現代全書
『日本の歴史 第07巻 武士の成長と院政』下向井龍彦著、講談社



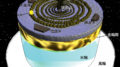




コメント