巻17第9話 僧浄源祈地蔵衣与老母語 第九
今は昔、比叡山の横川に僧がありました。名を浄源といいます。俗姓は紀氏(きのうじ)、慶祐阿闍梨(きょうゆうあじゃり)という方から瓶の水をうつすように(入室写瓶)教えを授かりました。長く山上に住み、顕教・密教の法を学びました。道心はたいへん堅く、一心に仏法を修行しました。
そのころ、飢饉が起こりました。飢える人渇く人がたくさんあり、餓死する者も続出しました。道に死体がすきまなく転がっていました。
浄源聖人の老母、そして妹は貧しく京の家で暮らしていました。食物はなく、死にかけていました。浄源は地蔵の本誓(貧しい者も富める者も老若男女すべてを利益する)を深くたのんで、ひそかに地蔵が現れる法を行い、「老母を助け給え」と祈りました。その行法が十七日に満ちようとす夜、京にいる老母の夢に、一人の美しい小僧が現れました。小僧は手に美しい絹三疋(びき、布絹の単位。一疋が二反)を捧げ、老母に言いました。
「この絹は上の中の上、最上の品です。横川の僧が私を呼んだので現れました。すみやかにこれ米にかえ、御要に宛てるとよいでしょう」
夢はそこで覚めました。目覚めて、夢を語りました。
夜が明けると、夢で得た絹がかたわらにありました。美し絹三疋です。人々はこれを見ると、手を打ち空を仰いで(感嘆したときのしぐさ)、「不思議なこともあるものだ」と思いました。
「現実に誰かが絹を持ってきたのを、寝ぼけて夢だと思ったのではないですか」
と尋ねてみましたが、訪れる人はありませんでした。怖ろしく思いましたが、従者の女にこれを持たせると、ある富裕な家に呼び入れられました。主人はこの絹を見ていたく感じ入り、米三十石(約4500㎏)と交換したといいます。
ある人がこれを伝えますと、浄源は涙を流したそうです。地蔵の悲願が正しかったことを貴び、悲しみました。
「私は老母の餓を助けるために、地蔵の誓を信じ、その法を行いました。すると、老母は夢に絹を得たといいます。ちょうど行法が十七日に満ちる日でした。これはまさに地蔵菩薩の利益です」
老母はこれを伝え聞くと、地蔵菩薩の利生を貴び、また浄源が孝行の心が深いことを喜びました。
この話を聞いて、多くの人が地蔵菩薩のありがたさに涙を流したと伝えられています。
【原文】

【翻訳】
草野真一
【解説】
草野真一
この話は『地蔵菩薩霊験記』(散逸)よりとったものとされる。『霊験記』には飢饉の詳細が記されており、長和年中(1012-1017)のこととある。『日本紀略』には長和四年三月に「天下咳病」「死者多矣」とある。
歴史家の説に、貨幣経済は南北朝時代まで浸透しなかったと語られているが、ここでも物々交換がおこなわれている。
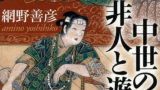








コメント