巻19第11話 信濃国王藤観音出家語 第十一
今は昔、信乃国(信濃国、長野県)に、筑摩の湯という湯がありました。人々はこれを薬湯と呼び、訪れては(治癒のために)浴びていきました。
あるとき、その里の人が夢を見ました。夢に人があらわれ、告げました。
「明日の午時(正午)に観音が来り給いて、この湯を浴み給う。縁(仏縁)を結びたいなら来るがよい」
「どのような姿でいらっしゃるのですか」
「四十歳ほどの、鬢(ひげ)を黒々と生やした男が、綾藺笠をつけ、節に黒漆を塗った矢を入れた大胡録を背負い、革を巻いた弓を持ち、紺の水干(狩衣)を着て、夏毛の行縢(むかばき、騎馬の防護用につける)を履いて、黒造の(黒漆を塗った)太刀を帯び、葦毛の馬に乗ってやって来る。それは観音だ」
そこまで聞いて、目がさめました。
驚き怪しみ、夜が明けてから、里の人にあまねく告げ廻り、語り聞かせました。これを聞いた人が次々とやってきて、湯に集まりました。すぐに湯を替え、庭を掃除し、注連(しめ縄)をつけ、香や花を備えました。多くの人が居並んで待っています。
やがて午を過ぎ、すこし日が傾いて未(午後二時)になるころ、夢で教えられた姿をした男がやってきました。風貌も服装も聞いたとおりで、まったく異なるところがありません。
男は人々に問いました。
「これは何事ですか」
しかし、人々はただ礼拝するばかりで、ことの次第を語る人はありません。男は手を摺り額にあて、礼している僧に問いました。ひどくなまっていました。
「これはどういうことですか。なぜ人々は私を見ておがむのですか」
「昨晩、人の夢に、しかじかと語られたのです」
男はこれを聞くと言いました。
「私は一両日前、狩をして馬から落ち、左のひじを折ってしまったのです。それを治療しようとしてこの湯に来ました。なのに、みなが私に礼しています。おかしな話です」
とにかく行こうとすると、すべての人がおがみながらついてきました。
「ならば、私は観音なのでしょう。私は法師になります」
男は庭に弓箭(弓矢)を棄て、兵仗を投げ、たちまち髻(もとどり)を切って、法師になりました。このように出家する様子を見て、人々はかぎりなく貴び感じ入りました。
そこにこの男を知っている人があらわれて、言いました。
「彼は上野の国(こうずけのくに、群馬県)の王藤(わとう)大主(敬称)です」
人々はこれを聞いて、彼を王藤観音と名づけました。
出家してからは比叡山の横川に入り、覚朝(覚超?)僧都の弟子になりましたが、五年ほど横川にいて、やがて土佐の国(高知県)に入りました。その後、彼がどうしているのか、聞いた人はありません。
不思議なことです。本当の観音がいらっしゃったのでしょうか。このように出家するとは、たいへん貴い仏であると語り伝えられています。
【原文】

【翻訳】 草野真一
【解説】 草野真一
不思議な話。
わけもわからず観音と呼ばれるようになってしまった人は出てくるが、彼はやがて消息不明になってしまう。リアルな観音は最後まで姿を見せない。
彼を王藤大主だと言った「知っている人」とは誰だろう。王藤観音とは、馬頭観音ではないかという説がある。彼がなまっているのも、東国から来たことを連想させる。
宇治拾遺物語に同じ話がある。
筑摩の湯とは、現在の湯の原温泉および浅間温泉(ともに長野県松本市)とされる。




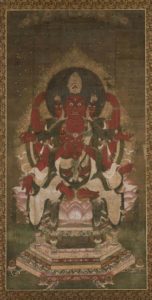






コメント