巻24第39話 藤原義孝朝臣死後読和歌語
今は昔、右近少将・藤原義孝(ふじわのよしたか)という人がいました。
この人は、一条の摂政殿(藤原伊尹)の御子であります。
容貌・人柄をはじめ、気立ても才能もすべて人にすぐれていました。
また、信仰心も深かったのですが、たいそう若くて世を去ったので、親しい人びとは嘆き悲しんではみたものの、どうすることもできませんでした。
ところが亡くなってのち、十月(とつき)ほど経って、賀縁(がえん・天台宗の高僧)という僧の夢に少将が現れ、たいそう気持ちよさそうに笛を吹いているように見えましたが、じつは、ただ口笛を吹いているだけでありました。
これを見て賀縁が、「母上があれほど恋い悲しんでおられるのに、どうしてそのように気持ちよさそうにしておられるのか」ときくと、少将は答えることなく、こう詠みました。
時雨には ちぐさの花ぞ 散りまがふ
なにふるさとの 袖ぬらすらむ
(俗世で時雨の降るころは、わが住む極楽浄土では、さまざまな花が咲いては散り乱れ、まことに楽しい思いをしている。それなのに、どうして古里の俗世では、いつまでもわが死を悲しんで泣いているのであろうか)
賀縁は夢がさめて驚いたのち、涙にくれました。
また、翌年の秋、少将の御妹の夢に、少将が妹と会って、こう詠みました。
着てなれし 衣の袖も 乾かぬに
別れし秋に なりにけるかな
妹は夢がさめて驚いたのち、ひどく泣き悲しみました。
また、少将がいまだ病床にあるとき、妹の女御は、少将が、「私が死んでもすぐには葬ってくれるな。お経を読んでしまいたいから」と言ったのですが、まもまく亡くなったので、その後、遺言を忘れて、その身を葬ってしまいました。
するとその夜、母の御夢に少将が現れ、こう詠みました。
しかばかり ちぎりしものを 渡り川
帰るほどには わするべしやは
(あれほど約束したのに、私が三途の川から立ち返る間に約束を忘れてしまわれるなどということが、あるものですか)
母は驚いて目覚めたのち、泣き惑いなさいました。
されば、和歌を詠む人というのは、死後詠んだ歌もこのようにすばらしいものである――とこう語り伝えているということです。
【原文】

【翻訳】
柳瀬照美
【校正】
柳瀬照美・草野真一
【協力】
草野真一
【解説】
柳瀬照美
本話は、藤原義孝が死後に肉親や知己の夢に現れて和歌を詠んだ逸話を一つにまとめたもの。巻15第42話は、義孝の往生について詳しい。
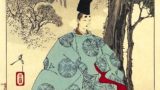
義孝の妹については、姉妹が多く、誰をさすか不明。女御になったのは、同母姉の懐子(かいし)で、冷泉天皇の女御にして花山天皇の母后。義孝が天延2年(974)秋に没したその翌年の春に亡くなっている。
この話では「女御が義孝の遺言を忘れた」とされているが、『大鏡』では、「母が忘れた」と記されている。
藤原義孝(ふじわらのよしたか・954-974)は、摂政太政大臣・藤原伊尹(ふじわらのこれただ)を父に、代明親王の娘・惠子女王を母として生まれ、同母兄の挙賢(たかかた)と同じ日、疱瘡(ほうそう・天然痘)によって、21歳という若さで亡くなった。正室の源保光(みなもとのやすみつ)の娘との間に、のちに三蹟として有名な行成(ゆきなり)がいる。
幼い頃から信仰心篤く、容姿がたいそう美しい人であったと伝えられている。
〈『今昔物語集』関連説話〉
藤原義孝:巻15「義孝の小将往生する語第四十二」
息子・藤原行成:巻24「円融院の御葬送の夜朝光の卿和歌を読む語第四十」
【参考文献】
小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』
『大鏡』佐藤謙三校注、角川書店









コメント