巻24第19話 播磨国陰陽師智徳法師語
今は昔、播磨国(はりまのくに・現在の兵庫県南西部)の□□郡に陰陽師のことをする法師がいました。
名を智徳(ちとく)といいます。
長年、その国に住んで、この道を行っていましたが、この法師は陰陽道に関して並々ならぬ力を持った奴でありました。
あるとき、□□国から多くの荷物を積んで京に上る船がありましたが、明石浦(あかしのうら)の沖で海賊が襲いかかり、船荷をことごとく奪い取り、数人の者を殺して逃げ去りました。
ただ船主と下人一人、このふたりだけが海に飛び込んで助かりましたが、陸に泳ぎ着いて泣いている所に、かの智徳が杖を突いて現れ、「そこで泣いているのは、どこの方じゃ」と訊けば、船主が、「国から上る途中、この沖で昨日、海賊に出会い、船の荷もみな取られ、人も殺されて、危うく命だけは助かったのです」と言うと、智徳が、「それは、まことに気の毒なことだ。そいつをここへ捕えて引き寄せてやろう」と言えば、船主は、「ただ口先だけだろう」と思いましたが、「そうしてくださったら、どんなにか嬉しいことでございましょう」と泣く泣く言いました。
智徳が、「それは昨日のいつのことかね」と問うと、船主は、「これこれの時刻でした」と答えます。
そのとき、智徳は船主を伴って小船に乗り、沖に漕ぎ出し、そのあたりに船を浮かべ、海の上に何か書き、それに向かって呪文を唱えてから、引き返して陸へ上がったあと、まるで、すぐそばにいる者を縛るかのような仕草をして、その道の人を雇い、四、五日監視させていると、船荷を奪い取られてから七日目の□□時ごろ、どこからともなく一艘の漂流船が現れました。
そこで漕ぎ寄せてみると、船中には武器を持った大勢の者が乗っており、それがすっかり酔っぱらったようになって、逃げもせずに打ち倒れています。
それはなんと、あの海賊です。
奪い取った荷は失われもせず、そのままであったので、船主のいうままにみな、こちらの船に運び取り、もとの持ち主へ返してやりました。
海賊どもは、その近辺の者たちが縛り上げようとしましたが、智徳が身柄をもらい受け、海賊どもに言い聞かせるには、「今後、このような罪を犯してはならぬ。本来なら打ち殺してやるところだが、それも罪になることであれば、この国にはこの老法師がおると心得るのだぞ」と言って、追い払ってしまいました。
船主は、ありがたい船出の準備と感謝して、出航して行きました。
これはひとえに、智徳が陰陽の術を用いて、海賊をうまく引き寄せた結果であります。
こういうわけで、智徳はじつに恐るべき奴でありましたが、清明に会い、自分の式神を隠されてしまいました。
とはいえ、それは式神を隠す法を知らなかったからで、特に術が劣っているとはいえないのです。
かような者が播磨国にいた――とこう語り伝えているということです。
【原文】

【翻訳】
柳瀬照美
【校正】
柳瀬照美・草野真一
【協力】
草野真一
【解説】
柳瀬照美
中世、なわばりを持ち、そこを通過する船から関銭を徴集し、払わなければ荷を強奪する海賊衆、後世の歴史家から『海の領主』と呼ばれた彼らも、古代ではそれほど組織化されておらず、海上で船舶を襲い、また海から攻め込んで陸上の人や物を奪う行為は、国司と郡司との対立、あるいは経済的な困窮から行われた。紀貫之の『土佐日記』には、海賊に襲われるかもしれないという不安を抱えての航海が描かれている。
播磨国というのは、能力のある民間陰陽師を輩出したらしい。蘆屋道満(あしやどうまん・道摩)もその出身だという。智徳もその一人で、24巻第16話で式神を清明に隠された法師は、智徳であったことがこの19話で明かされる。



【参考文献】
小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』
『海の日本史』中江克己著、河出書房新社
『海賊たちの中世』金谷匡人著、吉川弘文館

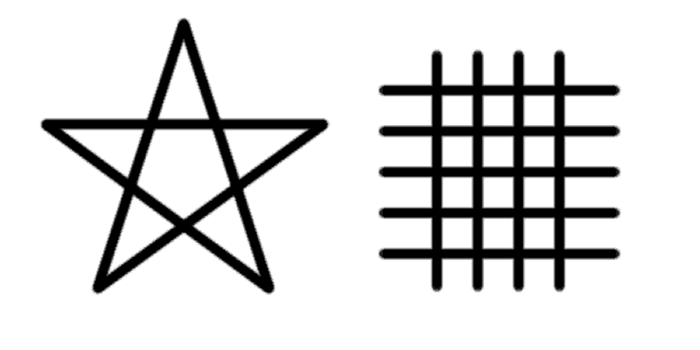

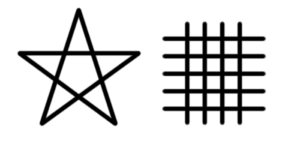





コメント