巻11第16話 代々天皇造大安寺所々語 第十六
今は昔、聖徳太子が熊凝の村(奈良県大和郡山市)に寺をつくりました。太子は完成を見ずに亡くなりました。推古天皇が後を継ぎました。推古天皇よりはじまり、聖武天皇に至るまで、九代の天皇が受け伝えつつこの寺をつくりました。
舒明天皇の御代に、百済河(平野川)のあたりに広い土地を選んで、熊凝の寺を移しました。百済大寺と呼ばれました。建造中にある行事官が近くの神社の木をこの寺の料として伐り用いました。神は怒り、火を放って寺を焼きました。天皇は大いに恐れましたが、寺の建造を続けました。
天智天皇の御代に、丈六(一丈六尺、約4.85メートル。仏像にもっとも適当とされる大きさ)の釈迦の像をつくり、祈願しました。その夜の暁に、天皇の夢に三人の天女があらわれました。美しい花をもって仏を供養し、敬い讃えました。
「この仏は霊鷲山にいらっしゃる真実の仏と変わりません。形もすこしも異なっていません。心をつくして崇めなさい」
天女たちはそう言って空に昇りました。そのとき夢から覚めました。仏像の開眼供養の日、紫の雲が空に満ち、妙なる音楽が天に聞こえました。
天武天皇の御代に、高市の郡(奈良県橿原市)に地を撰び、この寺を改め移しました。大官大寺と呼びました。天皇が塔を起てました。
天皇は言いました。
「釈迦の丈六の像をここに移す。よい工を得させてください」
そう祈願した夜の暁に、天皇の夢に一人の僧があらわれ、申しました。
「この仏をつくった者は化人(仏の化身)である。来てもらうのは難しい。よい工であっても、刀の誤りは必ずある。よい絵師であっても、絵の具の混ぜようを誤ることがある。ならば、ただこの仏の御前に、大きな鏡を懸け、影を写して礼奉るとよい。彫像するのではなく、絵に描くのでもない。そのまま三身(仏の三身。応身・報身・法身)を備えるだろう。すがた形は、応身である。影を浮かべれば報身である。虚であることを知れば法身である。これ以上に功徳が勝ることはない」
天皇は夢から覚めると、驚き喜び、夢で見たように、一枚の大きな鏡を仏の御前に懸け、五百人の僧を堂内に請じて、大きな法会をひらいて供養しました。
元明天皇の御代、和銅三年(710)、この寺を奈良の都に移しました。聖武天皇がこれを受け伝えて造られようとするころ、道慈という僧がありました。心に智があり、世に重く貴ばれていました。大宝元年(701)、法を伝えるために震旦(中国)に渡り、養老二年(718)、帰国して天皇に奏しました。
「私が唐に渡ったとき、心の内で『帰朝したら大きな寺をつくろう』と思っていました。そのために西明寺の建物のありさまを写しとってきました」
これを聞いた天皇はとても喜び、「私の願がかなったのだ」と言いました。天平元年(729)、道慈に命じて、この寺の改修をさせました。すべてを道慈にまかせました。
中天竺、舎衛国(コーサラ国)の祇園精舎は兜率天の宮を学んでつくったものです。震旦の西明寺は祇園精舎を模してつくりました。わが国の大安寺は西明寺を模したものです。十四年かかって建造し、大きな法会をひらき供養しました。天平七年(735)、大官大寺は大安寺と改められました。
また、道慈は言いました。
「この寺の焼けたのは、高市の郡の子部の明神の木をつかったからです。かの神は雷神であり、嗔(怒り)の心火を出しました。その後、九代の天皇は、諸方に移転させましたが、その費はとても多かったのです。(寺を守るには法の力によるしかありません。大般若経を書き写させて法会をおこない、経を読ませ、歌舞を奉納して神の心を喜ばせ、寺を守らせました)
()内は欠文、『三宝絵詞』より補う
【原文】

【翻訳】 柴崎陽子
【校正】 柴崎陽子・草野真一



【協力】ゆかり・草野真一
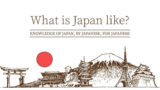












コメント