巻6第20話 江陵僧亮鋳弥陀像語 第二十
今は昔、震旦の江陵に僧がありました。名を僧亮といいます。極楽浄土をを願う心が深く、「阿弥陀仏の丈六(一丈六尺、約4.85メートル。仏像にもっとも適当とされる大きさ)の像をつくりたい」と考えました。しかし、その費用はとても高価で、何年たってもこれを成し遂げることはできませんでした。
僧亮は思いました。
「伝え聞けば、湘州(湖南省)の銅渓山の廟には、たくさんの銅の器があるという。それを所有し警護しているのは鬼神だそうだ。私はそこに行き、銅器によって阿弥陀仏の像を鋳造しよう。長年の願を遂げるとともに、その鬼神たちを導こう」
州の刺史(州知事)の張邵という人にこれを伝え、船と屈強な男百人を借り受けました。海を渡って行くためです。
張邵は言いました。
「廟は霊験あらたかで、犯す者があれば、みな死ぬという。また、蛮族が守護していて、近寄ることも難しい。恐るべきことだ」
僧亮は答えました。
「おっしゃることはもっともです。私がこの願を遂げて、その福をあなたに譲り、私が死にましょう」
張邵は感銘を受け、船も人も希望どおりに与えました。僧亮はこれを得てたいへんに喜び、船に乗り多くの人を率いて、かの銅渓山に至りました。
一晩もたたないうちに、鬼神はこれに気がつきました。すさまじい風が吹いて、黒い雲が覆って暗くなりました。多くの鳥獣が鳴き騒ぎました。廟屋の二十余歩前に、ふたつの銅の鼎(かなえ)がありました。とても大きく、数百石(一石は約100リットル)は納められるものでした。見ると、長さ十余丈(一丈は約3メートル)の蛇が、鼎の中から這い出て、道をふさいでいました。百人の従者たちはこの大蛇を見て恐怖し、逃げ散ってしまいました。
僧亮は服を整えて、大蛇に進み寄り、錫杖を振りながら言いました。
「おまえは前世の罪業が重かったからこそ、大蛇の身を受けて、三宝(仏法僧)の名を聞くことができない。私は『丈六の阿弥陀仏の像を鋳造したい』と思い、ここに銅の器があると聞いて、遠方から来た。道を開いてもらいたい。この願を遂げ、おまえたちを導きたいと思っている」
蛇はこれを聞くと、頭を持ち上げて僧亮のすがたを見ました。蛇は身を引いて去りました。
僧亮は逃げ散った数人を呼び集めて率い、銅器を取りました。さらに、林のあたりに四升は納められる壺がありました。内に長さ二尺余ほど(一尺は約30センチ)のトカゲがあり、壺から躍り出てきました。僧亮はこれを見て、恐れおののきました。
このような銅器はたくさんありましたが、大きなものは重いため取らず、小さなものだけを選んで船に積みました。
廟を護る人は僧亮を拒みませんでした。僧亮は都に帰り、願の丈六の阿弥陀仏の像を鋳造し、元寿九年(西暦432年)、造り終えました。
神もこれを過(とが)とはせず、像は端厳威光を現じたと語り伝えられています。
【原文】

【翻訳】 西村由紀子
【校正】 西村由紀子・草野真一
【解説】 西村由紀子
文中に「海」と記されているが、大陸に海があることはあり得ない。鬼神が銅器を守っているのは湖南省であるから、おそらくは洞庭湖(淡水湖)および長江のことだろう。いずれも日本には存在しないスケールであり、日本人が想像する湖や大河(琵琶湖や信濃川)よりも、むしろ海に近い。
「銅器は蛮族が護っている」という表現は、異民族(漢民族以外の民族)が住む島があったことを推測させる。



【協力】ゆかり・草野真一
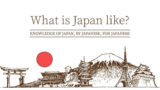










コメント