巻11第10話 伝教大師亙唐伝天台宗帰来語 第十
今は昔、桓武天皇の御代に、伝教大師という聖がありました。俗姓は三津の氏、近江の国志賀郡(滋賀県大津市)の人です。幼いときより賢く、七歳になるころには、明らかな智恵があり、多くのことを知っていました。父母はこれを怪しく思いました。
十二歳で頭を剃り、法師となりました。はじめて比叡山に入り、草庵をつくって、仏の道を行っているとき、香炉の灰の中に、仏の舎利(遺骨)が出てきました。おおいに喜びつつ、「この舎利を何に入れたらいいだろう」と考えているとき、灰の中に金の華器が出てきました。舎利をこの器に入れて、昼も夜も礼拝恭敬しました。
そのとき思いました。
「私はここに伽藍を建立して天台宗の法を弘めよう」
延暦二十三年(西暦804年)、唐に渡りました。まず天台山にのぼり、道邃和尚という人に会い、天台宗の法文を習いました。また、順暁和尚という人について、真言の教えを受けました。顕密(顕教と密教)の法を瓶の水を写ように習いました。仏隴寺の行満座主は日本の沙門を見て言いました。
「昔、智者大師(天台智顗)が言うのを聞いた。『私が死んでから二百余年たつと、東の国から私の法を伝え、世に弘めるために沙門がやってくる』。今わかった。この人がそうなのだ。早く法文を受け、本国に帰り、弘めなさい」
法は瓶の水をうつすように伝えられました。
唐に渡る前、まず宇佐の宮に詣で、
「旅の間、海難なく、平和に渡してください」
と祈りました。願いのように無事に彼の国に渡り着き、天台の法文を習いました。延暦二十四年(805年)に帰朝すると、そのお礼をするために、まず宇佐の宮に詣で御前に礼拝恭敬し、法華経を講じて言いました。
「私は念願のとおり唐に渡り、天台の法文を習って帰って来ました。今は比叡山に寺院を建立し、多くの僧徒を住ませ、唯一無二の一乗宗(法華経を真実の教えとする宗)を立て、有情非情皆成仏(すべてのものは仏になれる)を悟らせて、国に弘めたいと思っています。薬師仏をつくり、一切衆生(生きるものすべて)の病を癒やしたいと思います。ただし、その願いは、大菩薩(宇佐の神、八幡大菩薩)の御護があって遂げられるものです」
そのとき、御殿の内より妙なる声がありました。
「聖人の願いはとても貴いものだ。すみやかに願を遂げよう。私はもっぱら護りを加える。この衣を着て、薬師の像をつくりなさい」
御殿の中から衣が投げ出されました。取り上げて見ると、唐の絹(高級品)を濃い紫の色に染め、綿を厚く□した小袖でした。これを給わり礼拝して出ました。その後、比叡山に寺院を建立するとき、この浄衣を着てみずから薬師像を造りました。
また、春日の社に詣でて、神の御前で法華経を講ずると、山の峰より紫の雲が立ち、経を説く庭をおおいました。
こうして、願の如くこの国に天台宗が弘まりました。その後、この流れは所々に伝えられていきます。また、さまざまな国(地方)がこの宗を学び、天台宗は今もさかんだと語り伝えられています。
【原文】

【翻訳】 柴崎陽子
【校正】 柴崎陽子・草野真一
【解説】 柴崎陽子
最澄と空海
平安仏教は最澄と空海によって開かれました。
このふたりは同じときに海を越えて唐に留学するのですが、まだ独自の宗派をひらいていないこの時点で、両者の相違はあきらかになっていると言うことができるかもしれません。
長安の青龍寺に入り、当時最新の思想であった密教を得て帰国した空海にたいし、最澄は天台山(浙江省天台県)に向かいます。天台仏教の中心であることは間違いないが、ハッキリ田舎だと断じてもいいでしょう。密教はその合間にちょっと習ったという感じだったと伝えられています。
最澄の偉大は、帰国後、年下であり格下でもある空海の弟子となり、密教を学ぼうとしていることです。国家鎮護の法でもある密教が当時の為政者に求められていたという側面はあるでしょうが、そうそうできることではありません。
日本の密教はこの後、東密(真言系)と台密(天台系)にわかれます。台密はやがて最澄の弟子筋である円仁・円珍などによって完成を見ますが、密教の教主・大日如来を釈迦如来と同体とする(円密一致)台密にたいし、東密は別体とします。そこに大きな相違があるのですが、同じ密教であり所作もとてもよく似ています。
イスラム教などに顕著ですが、なまじ似ているからこそ反目がはげしくなるのです。東密と台密はこの後、ことあるごとに対立することになります。
比叡山は仏教の総合大学となり、のちに花開く鎌倉新仏教(浄土宗、浄土真宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗など)の誕生の母胎となりました。一派をなすような優れた弟子を輩出できなかったのは、空海の天才ゆえであると評されることも多くなっています。
八幡大菩薩と神仏習合
この話では最澄が入唐前と後に宇佐に詣でたことが語られていますが、これは現代においてはないことです。八幡神とは応神天皇であるとされ、日本の神です。しかし当時は八幡大菩薩(菩薩は仏教由来、インド生まれの概念)として崇められていました。いわゆる神仏習合です。
明治政府の政策によって、神仏は分離させられ、僧侶が神社に参るということもなくなりました。八幡大菩薩という呼称も廃止されます。
日本では生まれるとお宮参りをして神社を参拝し、キリスト教の教会で結婚式をあげ仏教で葬式して寺院に埋葬されるスタイルが定着しており、その一貫性のなさが批判されることもありますが、ひとつだったそれを分かつ神仏分離政策がこの結果を招いたと言ってもいいでしょう。責任の一端は明治政府の政策にあると考えていいと思われます。




【協力】ゆかり・草野真一
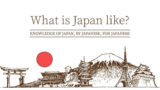













コメント