巻17第44話 僧依毘沙門助令産金得便語 第四十四
今は昔、比叡の山に僧がありました。やんごとなき学生(がくしょう)でしたが、とても貧しい人でした。裕福な檀家なども持たなかったので、比叡山にはいられなくなって、京に下って、雲林院というところに住んでいました。父母などもなかったので、暮らしのよりどころとするような人もありませんでした。年来、鞍馬寺にそのことをお祈り申しあげていました。
九月二十日ごろ、鞍馬に参ることがありました。帰り道、出雲路のあたりで日が暮れてしまいました。まずしい小法師ひとりを供に連れているだけでした。月が明るかったので、足早に帰路を急ぐうち、一条の北にある小路で、年は十六、七歳ばかり、とても美麗で好ましい少年と一緒になりました。少年は白い衣をしどけなく着こなし、帯を結んでいました。
僧は思いました。
「おそらくは寺の童(稚児)だろうが、供に法師がないのはおかしい」
童は近くに歩み寄ってきて、僧にたずねました。
「御房はどこにいらっしゃいますか」
「雲林院に戻るところです」
そう答えると、童は「私をつれていってください」と言います。
「どこの誰とも知らない人を、無責任に連れていくことはできません。あなたは、どういう理由で歩いているのですか。師のところへ行くのですか。母のもとへ行くのですか。『つれていってくれ』というのは、うれしい申し出ですが、後で妙な噂が広まっては困ります」
「そう思われるのは当然でしょうが、長年なじみだった僧と仲違いして、この十日ほど、さすらっています。両親とも幼くして別れましたから、かわいがってくれる人があるならば、お供をしてどこへでも、と思っているのです」
「とても嬉しいことです。後でとやかく言われようとも、私の咎(とが)にはならないでしょう。しかし、私が住む房には、貧しい小法師が一人あるばかりです。きっと退屈して、さみしく思うにちがいありません」
そう語りましたが、童はとても美しかったので、僧はすっかり心をうばわれ、ともに雲林院の房に向かいました。
火をともして見ると、肌は白く、顔はふくよかで愛敬があり、かぎりなく気高い童でした。僧はとても嬉しく思って、
「下臈(身分が低い者)の子ではないだろう」と考えました。
ところが、「父は誰ですか」と問うても、何も答えません。寝所をふだんよりつくろい、傍に臥して、物語して寝ました(寝物語)。やがて夜が明けると、隣の房の僧たちは、この童の美しさを褒め称えました。
僧は童を人に見せず、延(縁側)にさえ出さず、かわいがって、心にすきまもなく思い続けました。次の日も暮れました。僧は童に近寄り、今はなれなれなしくふるまいながら、ふと怪しい疑いを抱きました。
「私はこの世に生まれてから、母の懐以外に女の肌をさわったことがありません。だからよく知りませんが、あなたは通常の稚児たちに触れたときとは異なるように思います。心がとろけてしまうように思えるのです。ひょっとすると、あなたは女ではないでしょうか。そうならば、正直に言ってください。今はこういう仲になり、片時でも離れることはできませんが、あなたを怪しく、心得ず思うことが多いのです」
童は笑いながら言いました。
「女であったなら、親しくしてもらえないのですか」
「女性を連れているのは、世間にたいし遠慮があります。また、三宝(仏法僧)にたいしても、おそろしく思っています」
「あなたが自分から女犯するのなら、三宝がとがめることもあるでしょう。しかし、そうではありません。また、世間の人は童を連れていると思うにちがいありません。女であっても、世間には童であると語り、ふるまえばよいのです」
童はおもしろそうに笑いました。
僧はこれを聞いて、童を女だと確信し、怖しく悔しく思いました。しかし、すでに身にしみてかわいく思っていますから、追い出すこともできません。衣などで隔てて寝ていましたが、凡夫の悲しさでしょうか、打ち解けて、馴れ陸みあうようになりました。
僧は思いました。どんなにすばらしい童であっても、こんなにも離れがたく感じることはないだろう。「なにか前世に縁があるにちがいない」と思って過ごしていました。隣の房の僧たちは「これほど美しい若君を、あんなに貧しいのに、どうして得ることができたのだろうか」といぶかっていました。
やがて、童は胸のむかつきを訴え、食事できないことが増えました。怪しく思っていると、童が言いました。
「懐妊したようです。そのつもりでいてください」
僧はこれを聞いて、憂鬱になりました。
「人には童と言っていたのに、しばらくして懐妊したとはわびしいことだ。子が生まれたらどうするのだ」
「いつもどおりでけっこうです。あなたにご迷惑はかけません。ただ、そのときには、声をたてずにいてください」
僧は心苦しく、いとおしく思いながら過ごしました。やがて、月が満ちました。童は心細く、悲しいことを言って、泣いていました(産の恐怖と別れの予感が要因と思われる)。
僧もあわれに悲しく思っているうち、童は腹痛を訴えはじめました。
「生まれそうです」
僧はおろおろして騒ぐばかりです。
「騒がないでください。壺屋(しきられた部屋)に畳を敷いてください」
僧は童の言うままに、壺屋に畳を敷きました。童はそこにいて、しばらくすると子を産んだようでした。衣を脱いで子に着させ、乳をふくませて横になっているようでした。しかしそのとき、母は姿を消していたのです。
僧はとてもあやしみ、恐ろしく思って、近寄ってやおら衣をはいでみると、子はなくて、枕ほどの大きな石があるばかりでした。おそろしく、気味が悪く思いましたが、明るい場所で見ると、その石に黄色の光がありました。よくよく見れば金でした。
童は消えてしまいました。僧はありし日の姿を思い浮かべて、恋しくて悲しくてたまりませんでしたが、「鞍馬の毘沙門天が、私を助けようとしてくれたのだ」と考えました。
その後、金をすこしずつ砕いて売るたびに、豊かになりました。本来は黄金(きがね)であるのに、子金(こがね)と呼ぶのはこのためでしょうか。
弟子の法師が語りました。毘沙門天の霊験あらたかなのはこのようだと語り伝えられています。
【原文】

【翻訳】 草野真一
【解説】 草野真一
仏教は(すくなくとも伝統的には)僧侶の女犯と妻帯を禁じていた。では性処理はどうしていたのか。3つのパターンがあったと考えられる。
ひとつは、本当に戒律を守り、独り身をつらぬく場合。宮沢賢治は生涯童貞であり、一度も射精してないことを友人に自慢していたというから、少数ながらそういう人もあったのだろう。
もうひとつは、男色する場合。これはわりと一般的だったようで、空海と最澄も若い弟子の奪い合いをしている(瀬戸内寂聴はハッキリこれを男色関係だと言っている)。この文をみると、あまり罪の意識もなかったことがわかる。恥ずべきは女の恋人をもち妻帯することであり、男色の相手として若い稚児を連れることは認められていたのだ。
秘密裏に女性の愛人をつくることもあった。愛人を大黒様と呼んでいた。おそらくは私生児もあったことだろう。南方熊楠によれば高野山にも三味線の音が聞こえたそうだから、飲酒も女犯もある程度はおおっぴらにおこなわれていたと推測される。
*
『新日本古典文学大系36 今昔物語集4』(岩波書店)にも指摘されているが、この体験を鞍馬寺の毘沙門天の霊験としているのはあくまで僧の主観であって、実際はどうだったかわからない。とはいえ、鞍馬寺の話とされることで伝承の契機を得ているのもまた事実である。
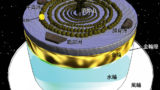



【協力】株式会社TENTO









コメント