 巻二十四(全)
巻二十四(全)巻二十四第二十七話 死んだ詩人と詩を解する下女の話
巻24第27話 大江朝綱家尼直詩読語 今は昔、村上天皇の御代に、大江朝綱(おおえのあさつな)という文章博士がいました。 たいへん優れた学者であります。 長年、文章道をもって朝廷に仕え、少しも心もとない点がなく、ついに宰相(さいしょう・...
 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全)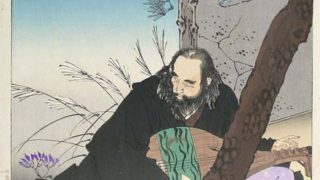 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全)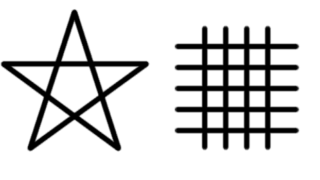 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全) 巻二十四(全)
巻二十四(全)